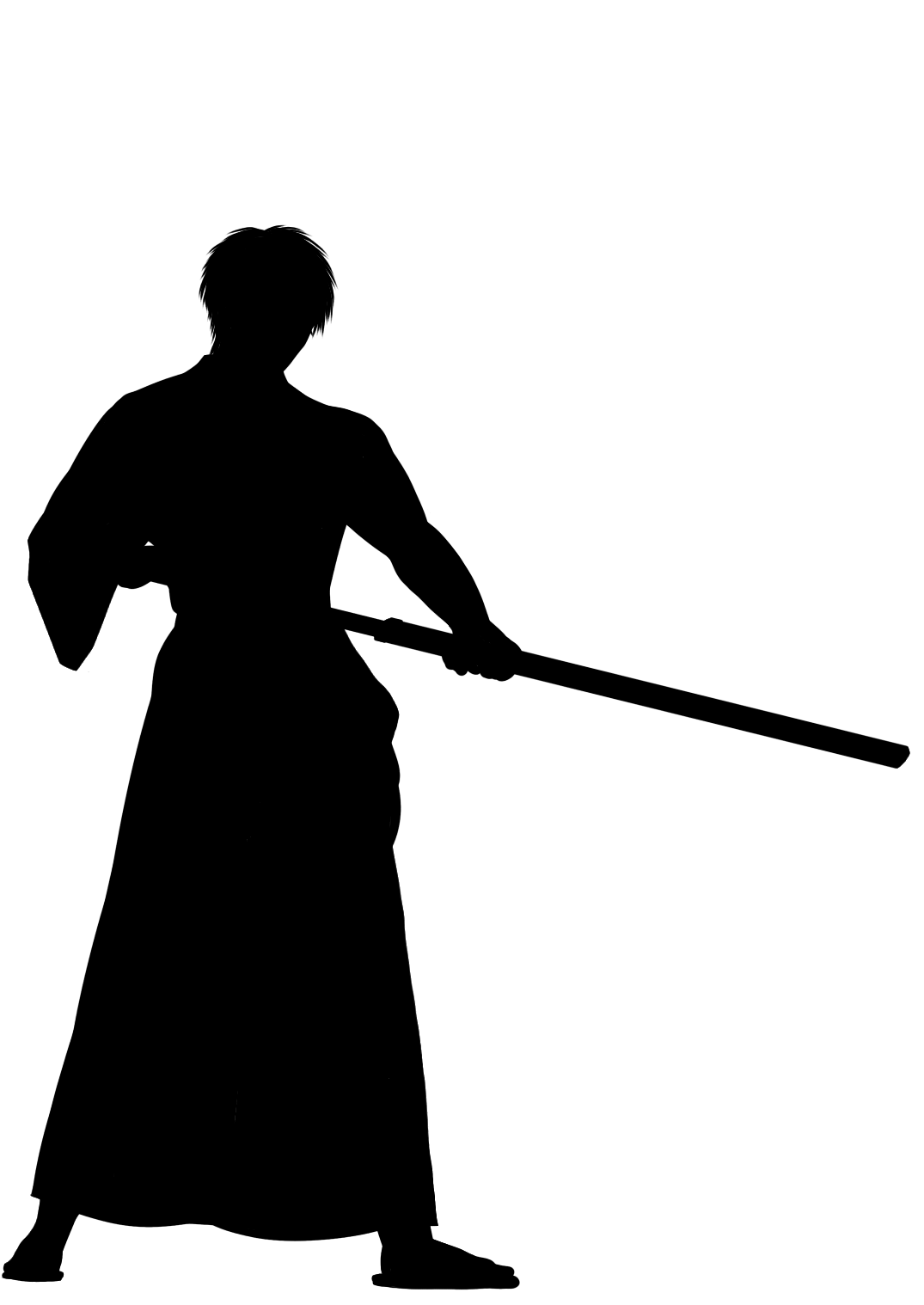日本刀の歴史は国史や神道とも繋がっていることから、刀剣は古代よりずっと神聖視されてきました。江戸時代にまで至ればもうわざわざ話を創らずとも、皆日本刀を崇め奉っていたはずですが、それでも徳川幕府は念押しともいえる刀の神格化に勤しんだのです。
戦国時代までは身分を問わず、男は帯刀していました。武士は名刀を、庶民は護身具としての実用に耐え得る刀を所持したのです。この実態が様変わりしたのが江戸時代でした。江戸時代は基本的に武士以外の帯刀は認められていませんでした。これにより、刀はそれまでの「神道」という宗教性に加え、「武士の魂」という新たな神性を帯びるようになったのです。その契機として重要なのは、家康と綱吉の時代でした。綱吉は帯刀を武士に限定しましたから、その後は刀剣に纏わる作法の格調が高まることになりました。また家康は彼自身の関心から剣術を修め、一刀流や陰流の達人を重用して剣術の充実を図りました。
幕府の創始者である家康が惚れ込み、神格化したのが日本刀であったことから、後継の将軍の下でも日本刀は重んじられ、宗教色も相俟って独自の進化を遂げました。しかし江戸時代も末期になると開国の匂いが漂い始め、順天堂で蘭学を学んだ若い侍や、緒方洪庵の適塾で啓蒙された者たちは、刀の蒙昧な神格化に見切りをつけ、躊躇わずに売り払うようになったのです。得たお金で宴会を開いたり、日本刀を彫刻刀代わりにして柱を傷つけたりする者まで現れ、近代化の波が日本刀の文化に影響し始めていました。とはいえ日本刀の一定の神性(精神的支柱)が担保され続けたことも確かであり、維新期に活躍した勝海舟のエピソードにもそれが見て取れます。